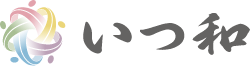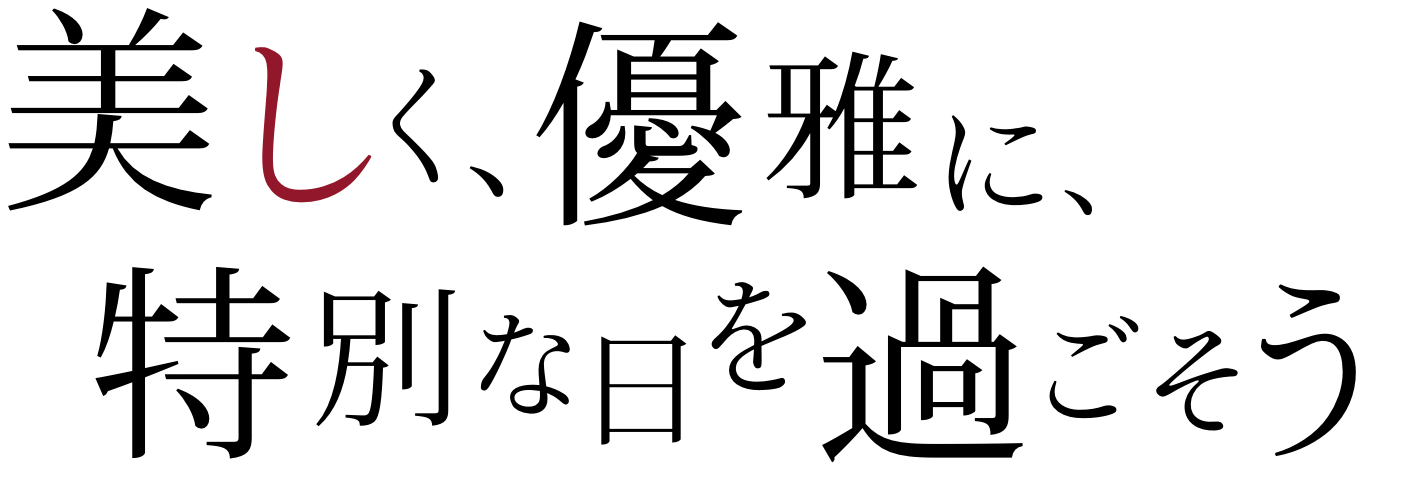
ひとりでも多くの人に
「着物や、ものづくりの
素晴らしさを伝えたい」
という私たちの想いが詰まっています。

コレクション
振袖のレンタル・購入・ママ振袖や、留袖レンタル、
着物お手入れとご希望に合わせたプランをご用意しております。
- 振袖
- 留袖
店舗案内
全国56店展開!お近くのいつ和店舗をお探しください。
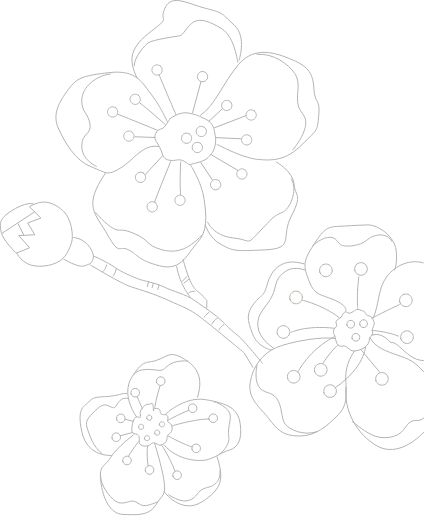
レンタルショップ


着物、浴衣をレンタルして、
街を散策しよう!
お知らせ
-
2026年度の最新振袖をアップしました。
2024.01.292026年度の最新振袖をアップしました。